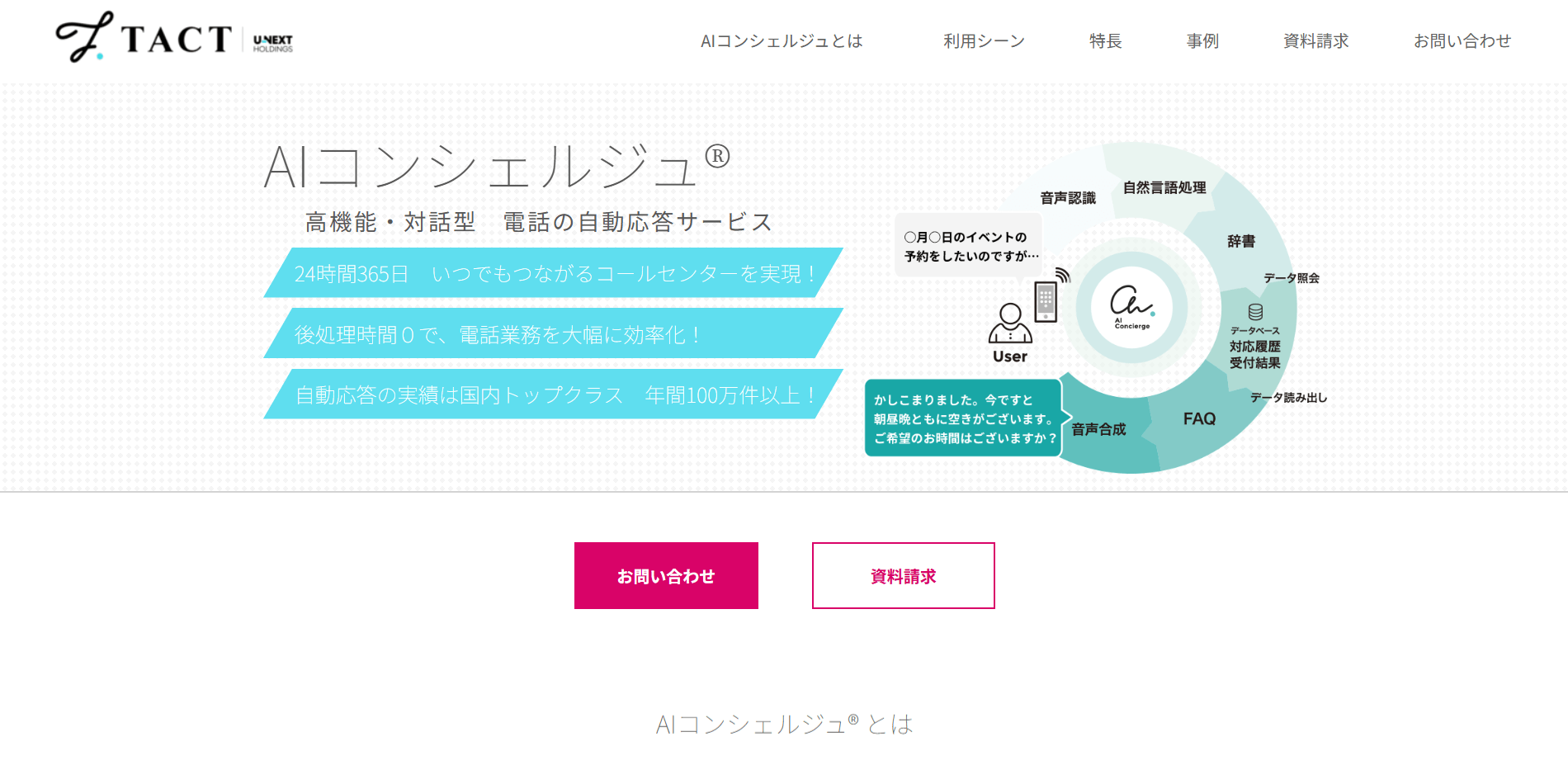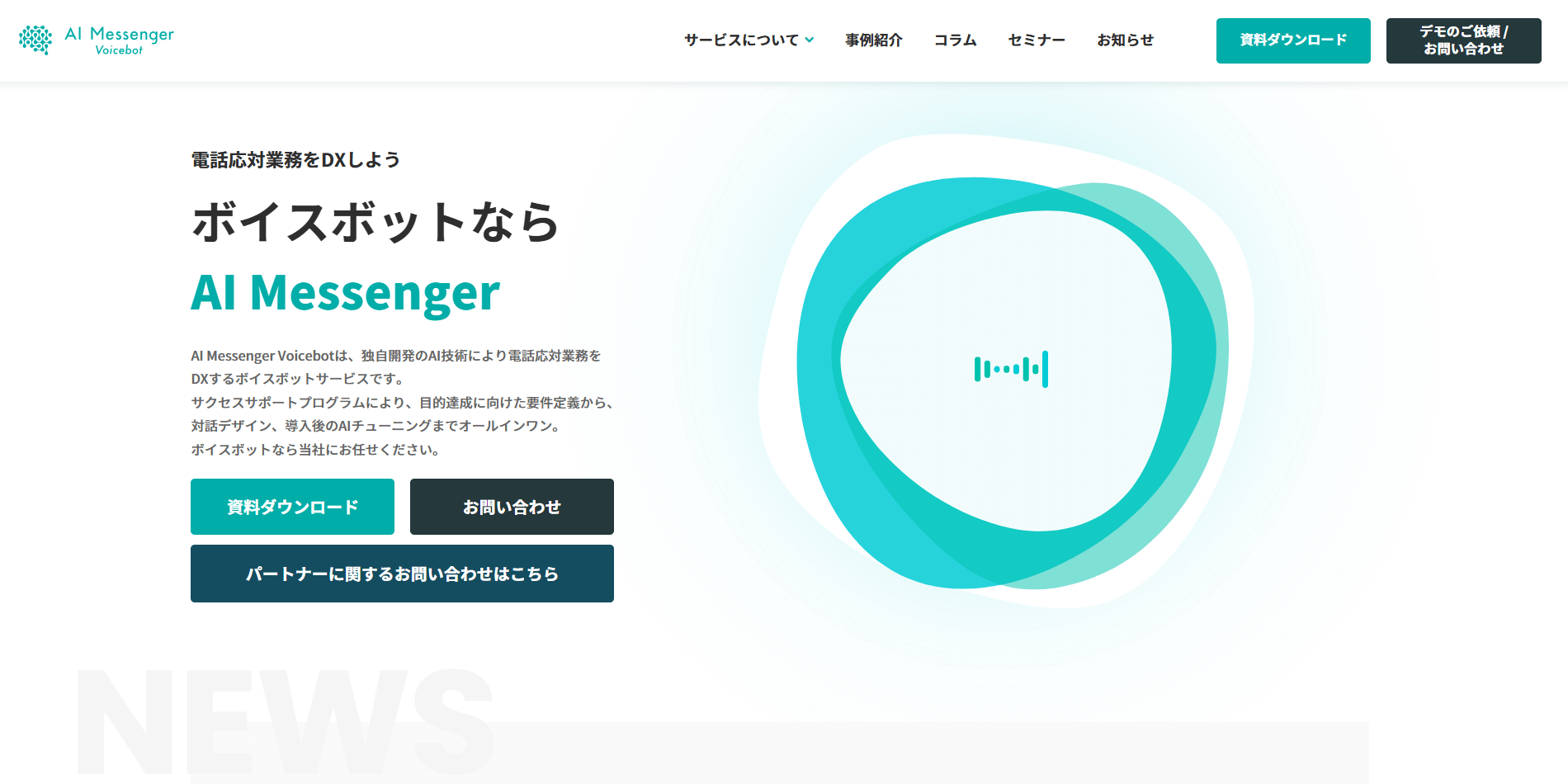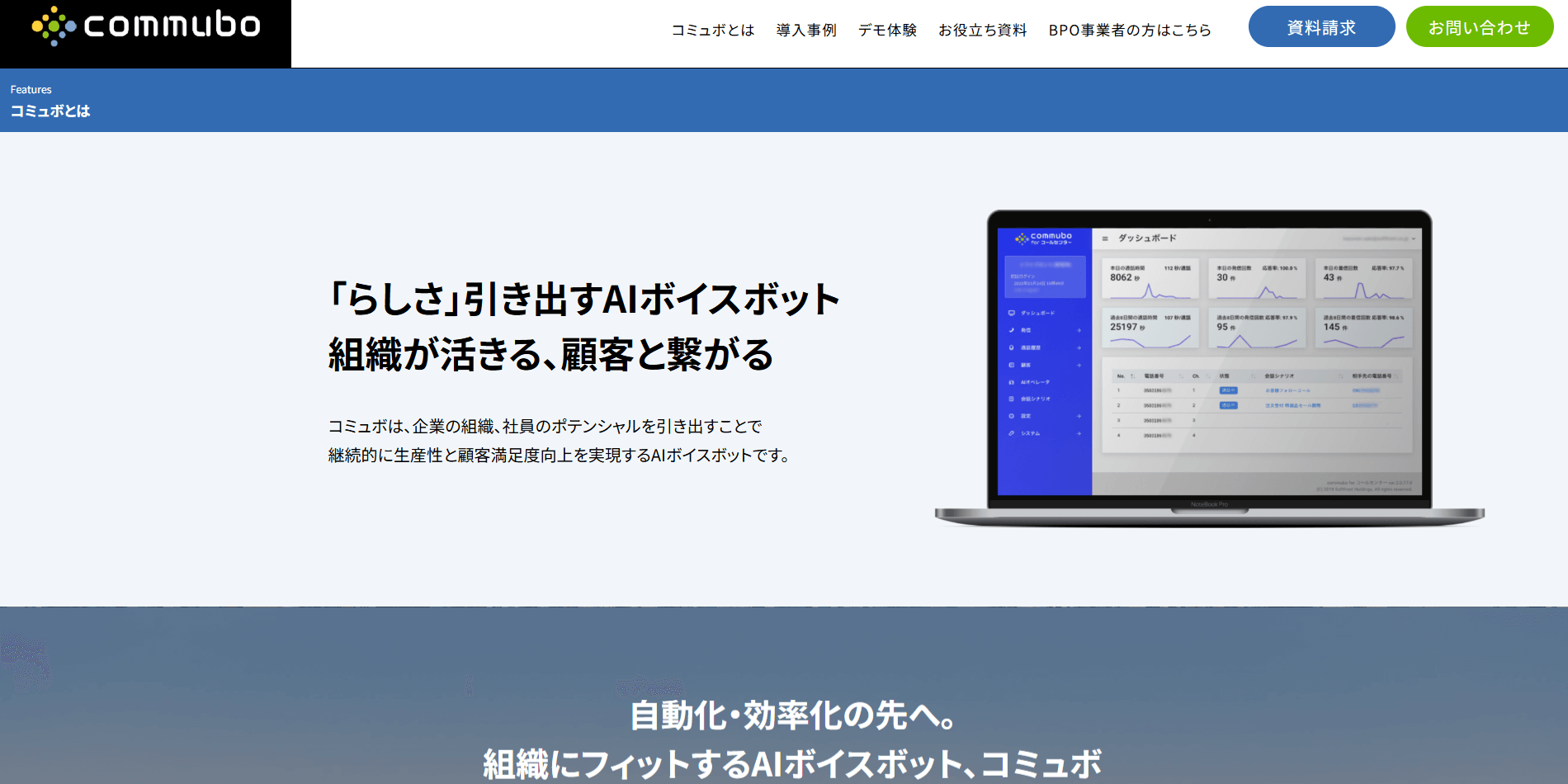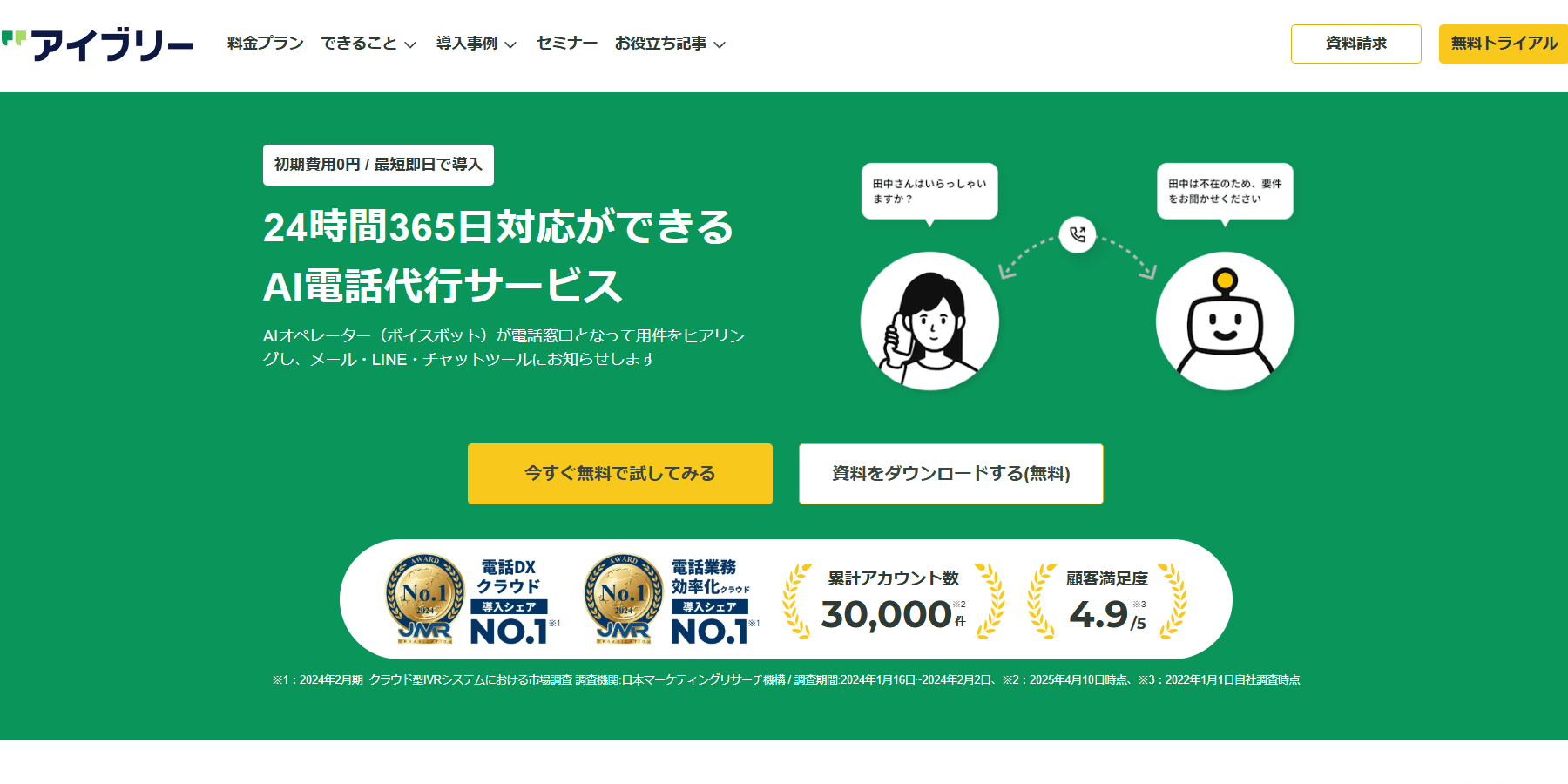近年、金融業界ではDXの推進が急務となっています。顧客のニーズが多様化し、競合との差別化を図るため、業務効率化や顧客満足度の向上が求められているためです。そこで、今回は、金融業界のDXを推進する、おすすめのボイスボットを3つ厳選して紹介します。それぞれの特徴や導入メリットについて、詳しく見ていきましょう。
目次
金融業界でDX化が急がれている理由
金融業界では、これまで対面でのサービス提供が中心でした。しかし、スマートフォンの普及やデジタル技術の発展に伴い、顧客の行動様式や価値観が変化してきています。銀行や証券会社の窓口に行かなくても、オンラインで手続きができるサービスが増え、顧客は、いつでもどこでも、自分の都合に合わせてスピーディーに利用したいと考えるようになりました。近年の時代の変化に対応するため、金融機関はデジタル技術を積極的に活用し、業務プロセスやビジネスモデルそのものを根本的に見直す必要に迫られています。
とくに、コールセンター業務は、多くの金融機関にとって顧客接点の最前線であり、さまざまな課題を抱えています。日々の膨大な入電件数にくわえ、顧客からの問い合わせ内容は多岐にわたり、オペレーターにかかる負担は大きいのが実情です。
また、定型的な質問への対応に追われ、本来注力すべき複雑な相談や高度なサービス提供に十分な時間を割けないという状況も発生しています。さらに、人手不足の深刻化や、ベテランオペレーターの退職によるノウハウの喪失といった、さまざまな課題を解決するためにDX化は重要な戦略となっています。
音声認識や自然言語処理といったAI技術を活用したボイスボットは、定型的な問い合わせを自動化することでオペレーターの負担を軽減し、顧客の待ち時間を短縮するなど、多岐にわたるメリットをもたらすでしょう。DX化により人手不足の解消のみならず、人件費削減にも寄与する可能性があることに加え、顧客対応の迅速化にもつながると考えられています。
DX化を進めることにより、金融機関は業務効率を大幅に向上させ、結果的に顧客満足度を高められるのです。
AIコンシェルジュ(株式会社TACT)

引用元:https://service.tactinc.jp/aic/
| 会社名 | 株式会社TACT |
|---|---|
| 住所 | 東京都渋谷区神宮前1丁目3番10号 |
AIコンシェルジュの利用シーン
AIコンシェルジュは、金融業界の多様な業務シーンで活用可能です。たとえば、口座開設やローン申し込みに必要な書類の案内、残高照会や振込手続きの説明など、定型的な問い合わせに24時間365日自動で応答できます。顧客は自身の都合の良い時間に情報を得ることが可能になるので、顧客満足度の向上が期待できます。とくに、コールセンターの営業時間外や、早朝・深夜といった時間帯の問い合わせにも即座に対応できるため、顧客の利便性を高められるでしょう。
さらに、AIコンシェルジュは、コールセンターの繁忙期における入電集中を緩和する役割も果たします。たとえば、キャンペーン期間中や新商品発売時など、問い合わせが殺到するタイミングでAIコンシェルジュが一次対応することで、オペレーターへの負担を軽減し、待ち時間の短縮も可能です。
オペレーターは、AIでは対応しきれない専門的な問い合わせや、顧客の感情に寄り添う必要がある相談に集中できるようになり、サービスの質を高められます。さらに、顧客の待ち時間が減ることで、顧客満足度の向上にも期待できるでしょう。
また、AIコンシェルジュの活用により、フロントエンドでのサービスの質が高まれば、企業のブランドイメージ向上も期待できます。
システム連携・SMS送信など多様な機能もポイント
AIコンシェルジュは、既存の基幹システムとのAPI連携やSMS送信など多様な機能が特徴です。SMS送信では、対話の最後にSMSで関連資料やURLを自動送信し、顧客が電話終了後すぐに必要情報へアクセスできる利便性を提供します。さらに、人による対応が必要な場面では、オペレーターへスムーズに転送することも可能です。くわえて、発話内容は音声とテキストで保存され、専用画面からいつでも履歴を確認できます。
また、プッシュ操作との併用や自動発信(オートコール)機能により、アウトバウンド業務や再架電にも柔軟に対応できることがAIコンシェルジュならではの強みです。
VoiceBOT(富士通株式会社)
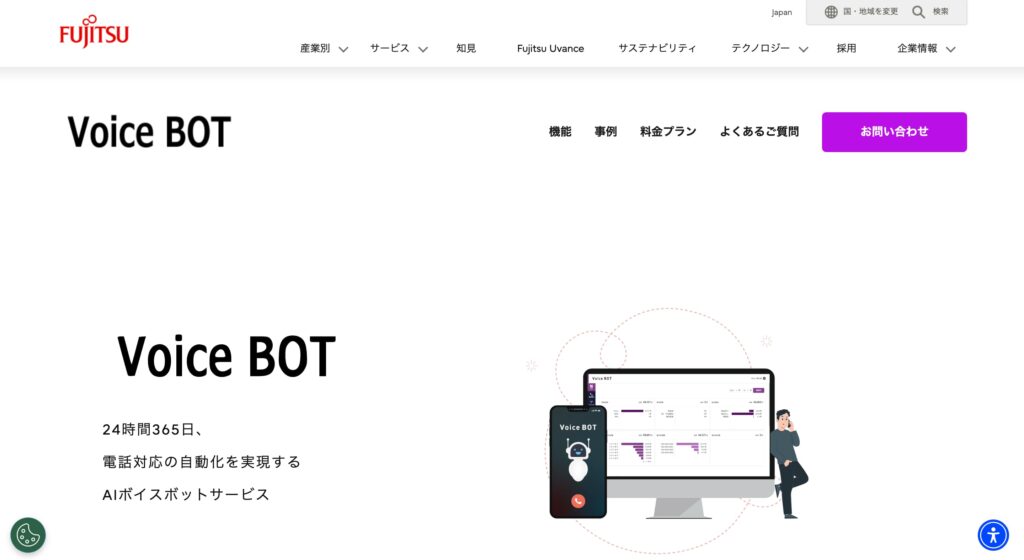
引用元:https://www.fujitsu.com/jp/services/knowledge-integration/chordship/voicebot/
| 会社名 | 富士通株式会社 |
|---|---|
| 住所 | 〒211-8588 神奈川県川崎市中原区上小田中4-1-1 |
応答率の向上率に貢献
VoiceBOTは、AIによる自動応答と有人オペレーターへのスムーズな引き継ぎを両立させることで、応答率の向上に貢献します。定型的な問い合わせはAIが自動で対応し、オペレーターはより複雑な案件に集中できるため、顧客の待ち時間が短縮されます。たとえば、残高照会やATMの場所案内など、頻繁にかかってくる問い合わせをAIが担当することで、オペレーターはより時間をかけて顧客の相談に乗ることが可能になるでしょう。
また、VoiceBOTは、24時間365日休むことなく顧客からの電話に対応可能です。営業時間外の問い合わせにも自動で応対することで、顧客は自身の都合に合わせていつでもサービスを利用できるのがメリットのひとつです。
いつでも対応が可能になるので、顧客接点を拡大し、新たなビジネスチャンスを創出することも期待できます。VoiceBOTは、単に業務を効率化するだけでなく、顧客満足度の向上、ひいてはビジネスの成長にも貢献するツールといえるでしょう。
VoiceBOTの導入により、緊急時の問い合わせにも迅速に対応できるため、顧客からの信頼も高まることも期待できます。
シナリオ機能や音声の自動テキスト化もポイント
VoiceBOTは、柔軟なシナリオ設定機能を備えている点が特徴のひとつです。金融機関のニーズに合わせて、問い合わせ内容や顧客の状況に応じた最適なシナリオを構築できます。たとえば、住宅ローンや教育ローンなど、商品ごとに異なるシナリオを設定することで、顧客を迷わせることなく、スムーズに目的の情報を案内できます。
また、顧客の発話内容に応じてシナリオを分岐させることで、よりパーソナライズされた対応も可能です。まるで人間と話しているかのようなスムーズな顧客応対で、満足度向上も目指せるでしょう。
さらに、VoiceBOTは、音声データを自動でテキスト化する機能も備えています。自動テキスト化機能により、AIと顧客の対話内容をすべて記録・分析することが可能になります。オペレーターへの引き継ぎの際も、テキスト化された対話履歴が共有されることで状況を素早く把握し、適切な対応をスムーズにおこなえるでしょう。
また、テキストデータを分析することで、顧客の問い合わせ傾向やニーズを把握し、サービス改善や新たな商品開発に役立てることも可能です。さらに、記録されたデータはコンプライアンス遵守の観点からも重要であり、電話応対の履歴を正確に残すことで、万が一のトラブルにも備えられます。
初期対応のみならず、履歴を残して継続的に顧客をサポートできるのがVoiceBOTの強みといえるでしょう。
PKSHA Voicebot(株式会社PKSHA Technology)

引用元:https://aisaas.pkshatech.com/voicebot/
| 会社名 | 株式会社 PKSHA Technology |
|---|---|
| 住所 | 東京都文京区本郷 2-35-10 本郷瀬川ビル 4F |
独自のエンジンを使用して高精度・高速度の対話体験を提供
PKSHA Voicebotは、PKSHA Technologyが長年培ってきたAI技術をベースに開発された独自のエンジンを使用しています。独自開発エンジンの導入より、高い音声認識精度と自然言語処理能力を実現しており、顧客はストレスなくボイスボットと対話可能です。たとえば、騒音のある環境や、早口で話す顧客の発話も正確に認識し、適切な応答を生成します。また、対話のレスポンス速度も速く、まるで人間と話しているかのようなスムーズなコミュニケーションが可能です。
さらに、PKSHA Voicebotは、顧客の発話内容をリアルタイムで理解し、フロー分岐機能で文脈に沿った適切な応答を生成できます。PKSHA Voicebotのフロー分岐機能により、従来のボイスボットにありがちな紋切り型の回答ではなく、顧客一人ひとりに合わせたパーソナライズされた対話が可能です。
PKSHA Voicebotの実際の導入効果を紹介
PKSHA Voicebotは、多くの企業で導入され、効果を上げています。ある保険会社では、ボイスボットの導入により、コールセンターの入電のうち、約70%の定型的な問い合わせを自動化することに成功しました。オペレーターは複雑な手続きや、顧客の心情に寄り添う必要がある相談に集中できるようになり、業務効率が向上しました。オペレーターの専門性が高まり、キャリアアップにもつながるという副次的な効果も生まれている一例です。
また、PKSHA Voicebotを活用して通話データを分析することで、よくある質問や問い合わせ傾向が可視化され、FAQ整備や業務改善にもつながっています。蓄積データを分析して活用することで、これまで以上に効率化を図ることができ、結果的に顧客満足度の向上を期待できるのです。
つまり、PKSHA VoicebotなどのDXツールにより、ツールを導入した金融機関は顧客満足度向上とコスト削減を同時に実現できるといえるでしょう。