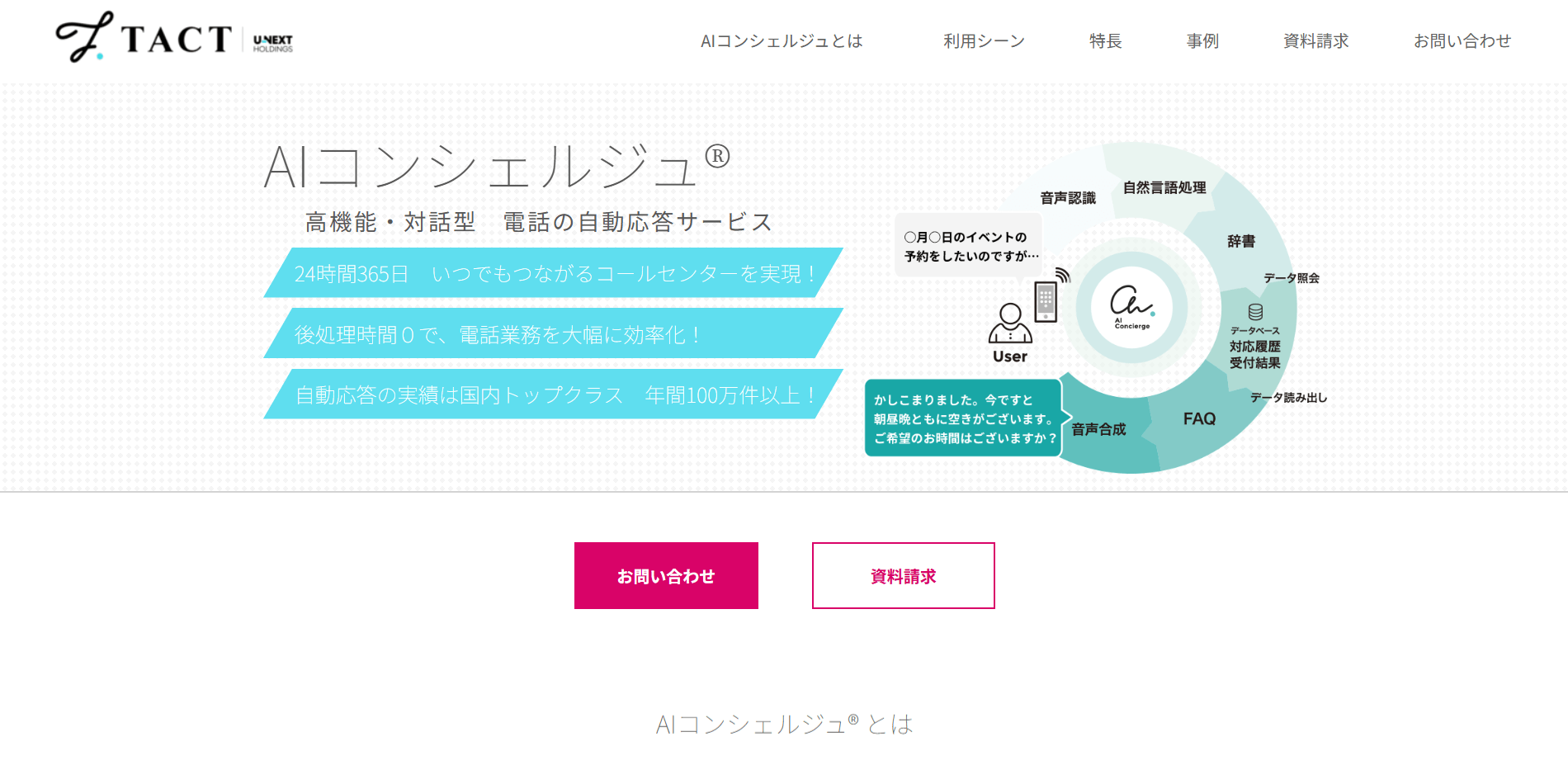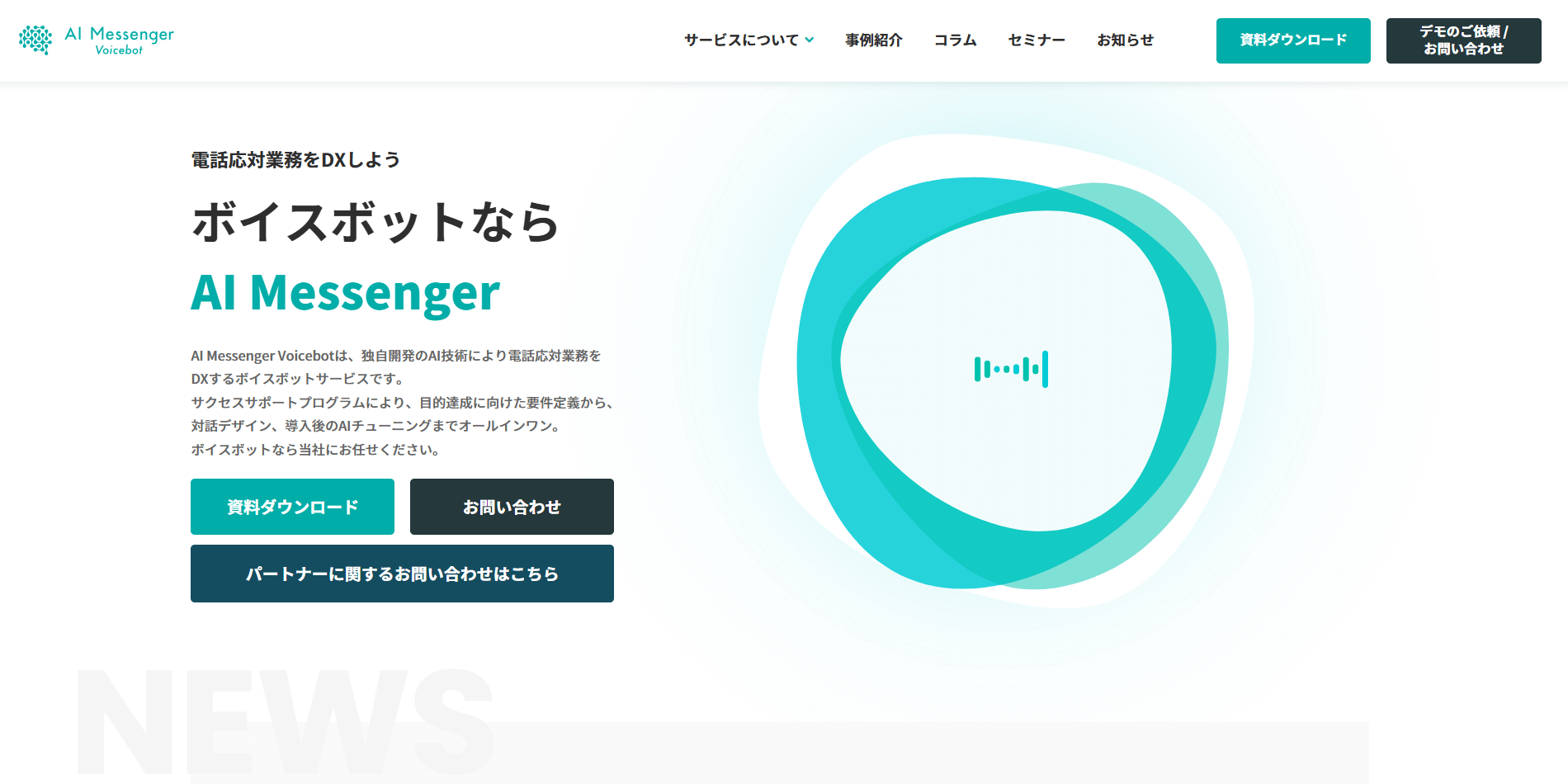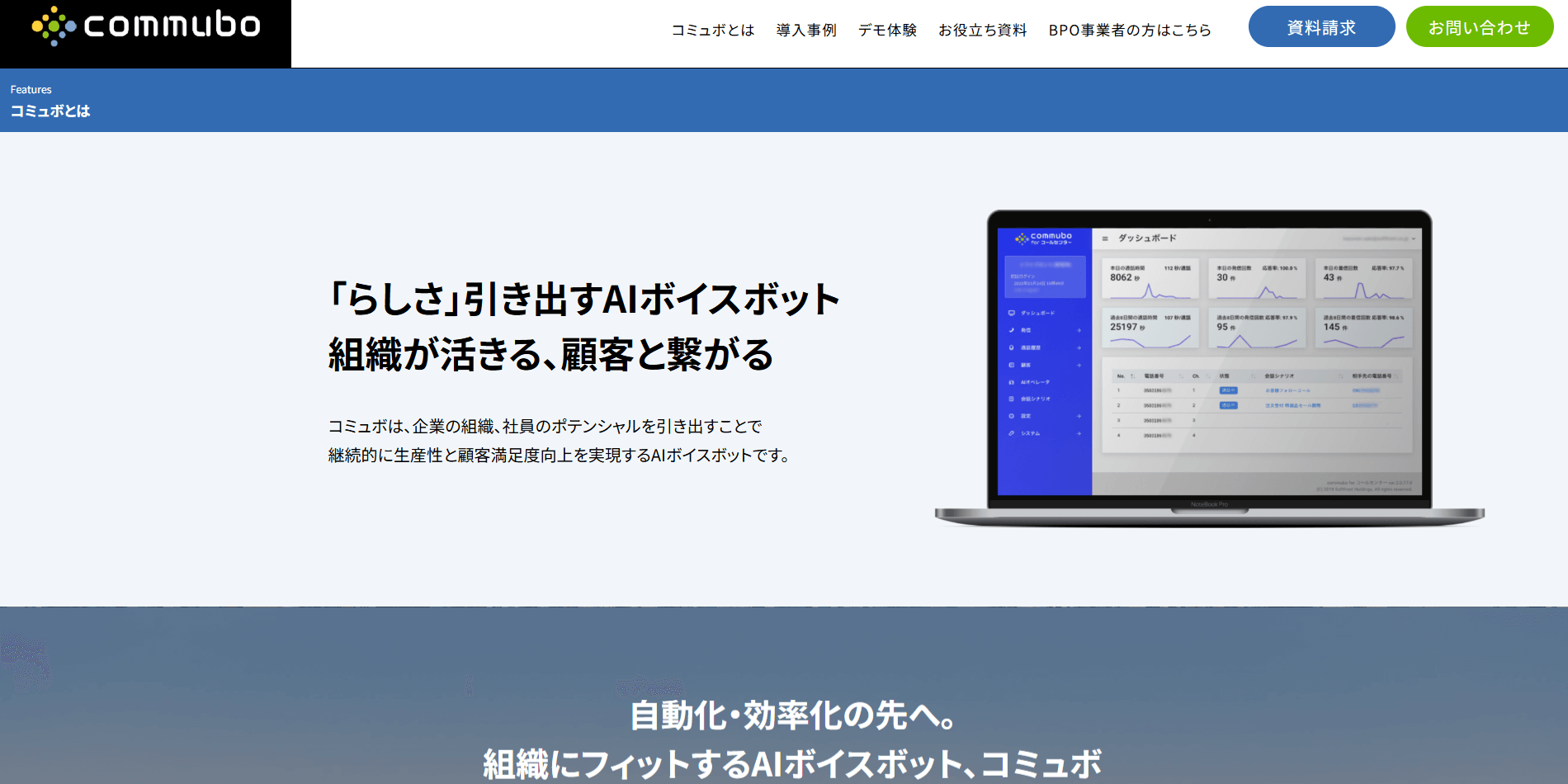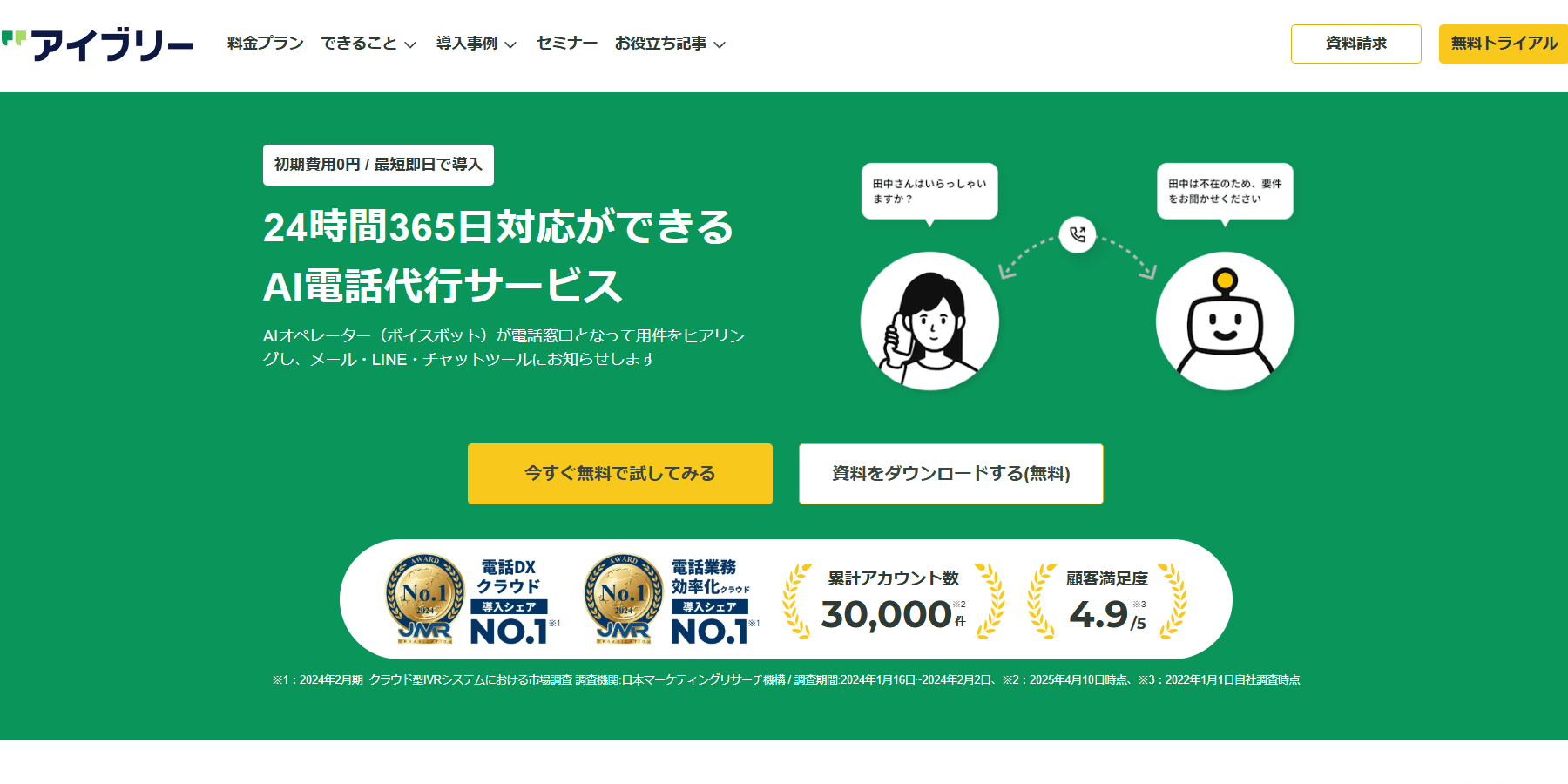昨今、多くの企業がコールセンターを設置し、顧客対応にあたっていますが、業界の中では「カスタマーハラスメント」が深刻な社会問題となっています。オペレーターの心身に負担をかけるだけでなく、企業の経営にも悪影響を及ぼすため、カスハラ対策は喫緊の課題です。そこで、今回はカスハラ対策に有効なAIソリューションを紹介します。
カスハラが社会問題になった背景
カスハラは、顧客が従業員に対しておこなう理不尽な要求や暴言、嫌がらせなどの迷惑行為全般を指します。問題が顕在化し、社会的な関心が高まった背景には、いくつかの要因があります。顧客至上主義
まず「顧客第一主義」と「過剰サービス」の文化が挙げられるでしょう。長い歴史のなかで、企業は顧客満足度を追求するあまり、過度なサービスを提供してきました。一部の消費者は「お金を払う側が偉い」「店員は要求に応えるのが当然」といった誤った認識を持つようになり、企業のていねいな対応を当たり前と見なすようになりました。結果として、少しでも期待に沿わないことがあれば、過剰な不満を表明し、クレームがエスカレートしてカスハラに発展するケースが増加しているのが現状です。
SNSの普及
次に、SNSの普及も要因のひとつです。今では不満を持った顧客が、SNS上で企業や従業員の対応を瞬時に拡散できるようになりました。企業側は炎上リスクを恐れ、事態を収拾するために顧客の要求を安易に受け入れてしまうことが多く、さらにカスハラを助長する悪循環を生み出しています。また、SNSでの拡散を恐れて企業が謝罪や賠償に応じる姿勢を見せることが「大きな声を出せば得をする」という間違った印象を一部の顧客に与えてしまっている側面もあるでしょう。
人々の余裕のなさ
さらに、現代社会における人々の心の余裕のなさも背景にあります。長引く不況やストレスフルな社会環境の中で、多くの人が心の疲弊を感じています。些細なことで感情的になりやすく、怒りをサービスを提供する従業員にぶつけてしまうという傾向が強まっているのです。
カスハラの現状について
カスハラは、顧客と従業員という関係性を逸脱し、一方的な攻撃性を向けることで発生します。カスハラが多くなっている状況を受け、厚生労働省がカスハラ対策に関する企業向けマニュアルを策定したり、一部の自治体で防止条例が制定されるなど、社会全体でカスハラ問題への意識が高まっているのです。しかし、根本的な解決には至っておらず、とくに人と直接向き合う機会の多いコールセンターでは、カスハラ問題がより深刻な課題として浮き彫りになっているのです。
従業員を守るための法的な枠組みはまだ十分に整備されておらず、企業側が自社の対策を強化することが強く求められています。対策の遅れが、多くの現場で働く人々を精神的に追い詰めているのが現状です。
コールセンターにおけるカスハラ問題とは
コールセンターは、顧客とのコミュニケーションの重要な窓口であるため、カスハラが発生しやすい最前線でもあります。電話という非対面でのやり取りは、相手の顔が見えないため、顧客の感情がより攻撃的になりやすい傾向にあるのです。コールセンターで発生するカスハラには、さまざまな種類があります。
暴言・人格否定
一般的な例が「暴言・人格否定」です。「お前は馬鹿か」「責任者を出せ」といった言葉は、オペレーターの精神を深く傷つけ、自己肯定感を低下させてしまうでしょう。不当・過剰な要求
また、「不当・過剰な要求」も深刻な問題です。商品やサービスに不満がある場合でも、本来の補償範囲を超える金銭的・物質的な要求を執拗に繰り返す行為は、業務を妨害し、ほかの顧客対応にも支障をきたします。執拗な嫌がらせ
さらに「執拗な嫌がらせ」もオペレーターを追い詰めます。同じ内容の電話を何度もかけ続けたり、長時間にわたって無意味な説教をしたりする行為は、オペレーターの精神的な疲労を蓄積させ、業務効率を低下させてしまうでしょう。カスハラがオペレーターにもたらす悪影響
カスハラ行為は、オペレーターに深刻な影響を与えます。精神的なストレスはうつ病や適応障害などのメンタルヘルス不調を引き起こすだけでなく、業務へのモチベーション低下や集中力の欠如につながります。結果として、オペレーターの離職率の上昇を招き、人手不足に拍車をかけることになるのです。経験豊富なオペレーターが辞めてしまうことで、コールセンター全体の応対品質が低下し、最終的には企業への信頼失墜にもつながりかねません。
そして、カスハラの被害に遭ったオペレーターは、次々と退職していくという負の連鎖が生まれてしまいます。カスハラ問題による人手不足は、企業の採用コストや研修コストを増大させるだけでなく、顧客対応の質そのものを損なうことに繋がってしまうでしょう。
カスハラ対応はオペレーターのスキルに依存しがち
また、カスハラへの対応は、オペレーターの個人的なスキルや経験に依存しがちです。ベテランのオペレーターは適切に対応できても、新人オペレーターはどのように対処すればよいか分からず、事態を悪化させてしまうリスクがあります。くわえて、コールセンターではCS(顧客満足度)向上の観点から、VOC(顧客の声)収集を目的として、クレーム対応もオペレーターの大切な業務と定めている会社もあります。しかし、苦情とカスハラを区別することは困難です。
さらに、現場では属人的な対応を求められることも多く、SV(スーパーバイザー)やセンター長へのエスカレーションが適切におこなわわれず、対応者が一人で苦しい思いを抱え込んでしまうケースもあるでしょう。属人化している問題は、組織全体としてのカスハラ対策を困難にしています。
カスハラ対策におすすめのAIソリューションを紹介
コールセンターにおけるカスハラ問題の解決策として、注目を集めているのがAI技術の活用です。AIソリューションは、オペレーターの負担を軽減し、カスハラを未然に防ぐための武器となります。ここでは、有効な3つのAIソリューションを紹介します。AIによるリアルタイム検知・切り替え機能
まずは、AIによるリアルタイム検知・切り替え機能です。AIが通話内容をリアルタイムで分析し、カスハラにつながる可能性のある兆候を検知後AI音声に切り替え、応対を引き継いでくれます。音声認識技術によって顧客の発言から、特定のキーワード(「どうしてくれるんだ」「責任者を出せ」など)や音声のトーン、声の大きさ、話すスピードなどを解析し検知します。切り替えは、手動と自動の両方で対応可能です。
自動の場合、AIが通話内容に含まれるNGワードを常に監視し、キーワードが検出されると即座に切り替わる仕組みです。AIが応対を引き継ぐと、カスハラに該当する言動があったことを警告する自動応答が流れ、顧客に対して冷静な対応を促します。
切り替え機能により、オペレーターは直接的な暴言から保護され、精神的な負担を軽減できるでしょう。現在は実証実験段階のため、具体的な事例はまだありませんが、今後、さまざまなコールセンターでの活用が期待されているソリューションです。感情的な対立の最前線からオペレーターを遠ざけ、問題の深刻化を防ぐための有効な手段となるでしょう。
AI音声変換ソリューション
次に、AI音声変換ソリューションで、顧客の攻撃的な発言を、オペレーターに聞こえる前に穏やかなトーンに変換して届けるという、画期的なソリューションです。これは、AIが顧客の音声から感情的な要素(怒りや威圧感)を検知し、内容を維持しつつも、声のトーンや抑揚を中和するという技術に基づいています。たとえば、顧客が怒鳴り声で「どうしてくれるんだ!」と言ったとしても、オペレーターには落ち着いた声で「どうしたらいいでしょうか?」のように聞こえるように変換されます。これにより、オペレーターは顧客の感情的な攻撃に直接さらされることがなくなり、精神的な負担を軽減できるでしょう。
AI音声変換ソリューションの利点は、オペレーターが常に冷静に対応できるという点です。顧客の攻撃的な言葉に動揺することなく、本来の業務である問題解決に集中できるため、応対品質の低下を防ぎ、迅速な対応を可能にします。
また、顧客自身も、オペレーターの冷静な対応に接することで、興奮状態が収まり、建設的な会話に戻れる可能性が高まるでしょう。ただし、まだ開発中の技術で、発展途上の部分もあります。音声の自然さやリアルタイム性など、今後のさらなる進化が期待されているソリューションでしょう。
AIボイスボットによる一次対応の自動化
最後は、AIボイスボットによる一次対応の自動化です。AIボイスボットは、顧客からの電話を自動で受け付け、一次対応をおこなうAIシステムです。簡単な問い合わせや用件の振り分けを自動化することで、オペレーターが対応する前に、カスハラになりうる可能性のある電話をフィルタリングする役割を担います。ボイスボットは、顧客の音声から問い合わせ内容を解析し、自動応答で解決できる用件であれば、そのまま対応を完了させます。
たとえば、よくある質問や手続きの案内、予約の変更といった定型的な業務は、ボイスボットが対応することで、オペレーターが対応する必要がなくなるでしょう。
ボイスボットの仕組みは、オペレーターが不当なクレームや暴言を浴びる機会を減らすことが可能になります。とくに、最初から感情的になっている顧客の場合、ボイスボットが一次対応することで、オペレーターに電話がつながる前に感情を鎮めてもらう効果も期待できます。
AIボイスボットは、オペレーターをカスハラから守るだけでなく、業務効率化とコスト削減にも貢献するソリューションです。オペレーターは、より複雑で専門的な対応に集中できるようになり、働きやすい職場環境の構築にも役立つでしょう。